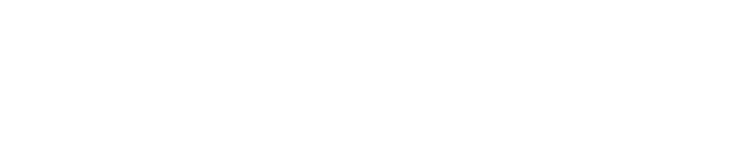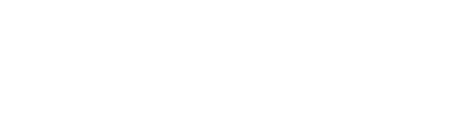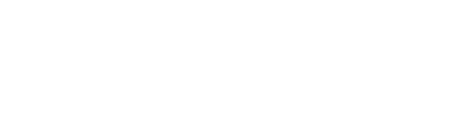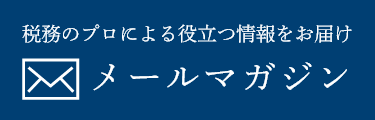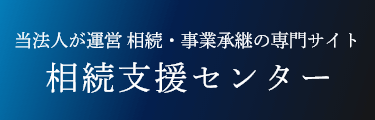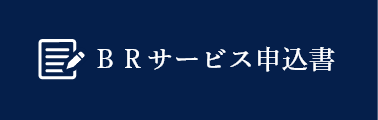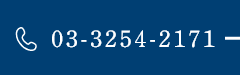Vol.0532
<タックスニュース>
固定資産税の過徴収で大阪市が最大50億円返還も 20年超の賠償を初認定か
大阪市が独自に規定した固定資産税の評価ルールを巡り、同税を過大に徴収された市民に対し、最大50億円分を返還する可能性が出てきた。同ルールを巡って争われている裁判で、国家賠償法の期限である20年を超える過徴収についても市の責任を認める可能性が高くなったためだ。固定資産税の過大徴収は全国で起きていて、数十年にわたって行われていた例も少なくない。来月24日に言い渡される判決次第では、全国の同様の事例に影響を及ぼす可能性がある。
固定資産税の税額を計算する基礎となる評価額は、原則として国が規定した「固定資産評価基準」が用いられる。しかし同税は地方税であるため、実際の運用に当たっては、一定範囲内で自治体ごとの独自ルールを用いることも認められている。
大阪市が訴えられたのは、マンションの構造に利用されていた「PHCくい」の評価方法。PHCくいについては、国が2005年に基準となる評価額を定め、自治体の裁量で最大5倍までの評価額を許容している。大阪市が定めていた評価ルールは国の上限を超えるものだったが、市が独自ルールを定めたのは国が基準を規定するよりはるかに以前の1978年だったため、これまで問題視されてこなかった。
しかし6年前に納税者が賠償を求めて裁判を起こし、最高裁まで争った結果、昨年12月に独自ルールの違法性が認められた。それを受けて大阪市は今年2月21日に、今後の対応として、同様の基準で過大徴収されてきた市民3万人に対し、過大分に当たる約16億円を返還する方針を発表している。
大阪市が返還するとした約16億円はそれだけでも大きな額だが、過大徴収してきた全額ではない。というのも、国家賠償法では税などの過大徴収について20年の時効を設けていて、大阪市もそれに従って2000年以降の20年分にのみ返還に応じるとしているためだ。独自ルールが設けられたのは42年前なので、過大徴収されてきた期間の半分以上は戻ってこないということになる。
そこで別の納税者が、20年を超えて市への請求権を求める裁判を起こしたところ、一審・二審では市が勝訴したが、最高裁は2月25日、原告と被告双方の主張を聞く弁論を開いた。弁論は二審判決を覆す際に開かれることから、「大阪市は20年を超えて過大徴収については返還すべき」と認められる可能性が高い。判決は3月24日に下される予定だ。
もし最高裁で納税者が逆転勝訴すると、大阪市はルールを規定した1978年以降の全ての過大徴収に対して返還する義務が生じる可能性がある。そうなれば返還額は最大50億円に達するとみられる。
さらに判決の影響は大阪市だけにとどまらない。例えば茨城県つくば市で17年に発覚した固定資産税の過大徴収は過去40年にわたって行われていたことが明らかになっている。市は国家賠償法に基づき20年分、約1億7千万円を返還したが、大阪市の判決を受けて納税者が20年を超える部分についても賠償を求めれば応じざるを得ないだろう。
地方税法では、固定資産税について土地の現況などを定期的に確認する事を求めている。しかし実際には、一度算定された税額は増築や取り壊しなどの変化がないかぎりノーチェックで据え置きにされることがほとんどで、一度誤った計算方法によって算定された税額が数十年にわたって放置されることも珍しくない。大阪市のような過大徴収は全国で発覚しているため、「次は自分の番か」と首をすくめて来月24日の判決を注視している自治体は多いはずだ。
税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ
<タックスワンポイント>
コロナで中国人客が激減 雇用調整助成金の要件緩和は条件アリ
新型コロナウイルスの流行で、国内の中小企業が深刻なダメージを受けている。政府は企業支援の一手として、このほど「雇用調整助成金」の要件緩和を決定した。
この補助金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者を対象に、労働者に支払う休業手当の一部を助成するものだ。中小企業であれば3分の2(1人1日当たり8335円が上限)が国から支払われる。
厚生労働省は同補助金の要件を、(1)休業等計画の事後提出が可能、(2)前年と売上を比較する期間を3カ月から1カ月に短縮、(3)直近3カ月の雇用状況を問わない、(4)事業所設置1年未満の事業主も対象――に緩和した。
いつもより助成を受けるためのハードルは低くなったが、注意したいのは、要件緩和の対象は、「中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の1割以上を占める」事業主に限定されている点だ。申請の際には、前年度の売上データや顧客リストなど中国人客の割合を証明できる書類の提出が必要だという。また「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主」ともあり、単純に中国企業との取引減で売上が落ちたなどのケースは対象とならない可能性がある。その場合は、緩和前の要件を
満たすことで助成を受けられる。