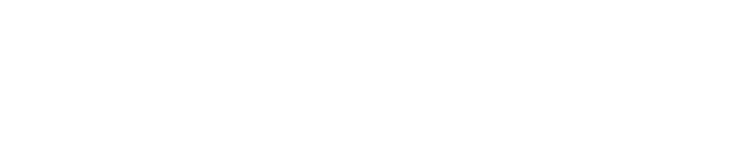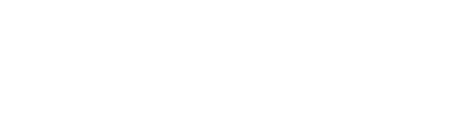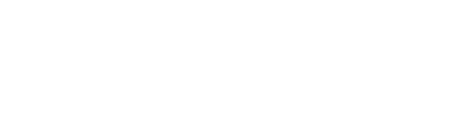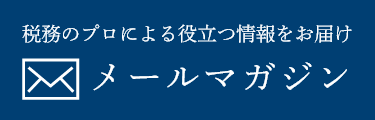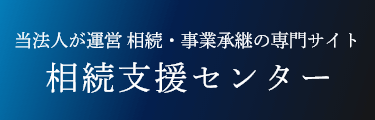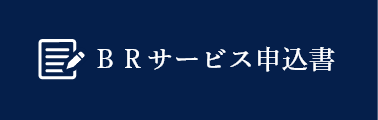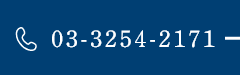Vol.0545
<タックスニュース>
持続化給付金の官製談合疑惑 火消しに躍起の経産省
新型コロナウイルスの感染拡大で減収した中小企業や個人事業主に現金給付する持続化給付金事業の民間委託を巡り、その実態が不透明だとして厳しい批判を招いている。所管の経済産業省は、通常は年度末に行う委託事業の検査を今月中に「中間検査」として実施すると表明し、火消しに躍起だ。
問題視されているのは給付金事業を受託した一般社団法人「サービスデザイン推進協議会」。今回、約769億円で受託し、広告大手の電通に約749億円で再委託した。電通はさらにグループ会社5社に外注し、このうちの一社である電通ライブは、人材派遣会社のパソナ、ITサービスのトランスコスモス、大日本印刷などに外注。20~30社が関与しているとみられるが、全体像は不明点が多い。
持続化給付金は約2.3兆円の巨大事業。野党は「委託や外注を繰り返し、東京都内の事務所には職員もいない。協議会は実態のないトンネル団体だ」と追及する。
協議会は電通やパソナなどが2016年5月に設立。定款のPDFファイルのプロパティが経産省のものだったため疑念をさらに強めた。ある霞が関関係者は「電通やパソナと組んで事業を丸投げするのは経産省の常とう手段。深く考えずにやったんだろうが、今回はコロナで苦しむ民意を読み誤った」と解説する。
一方、民間委託活用は行政改革の一環で今に始まったことではない。2兆円を超えるお金を申請から2週間以内に給付するという前例のない事業を行政で完結するのは困難だ。5月1日から開始し6月2日までに約150万件の申請のうち約100万件、1兆3400億円の給付をすでに実施した。別の関係者は「民間委託が悪いとは思わない。あとはどう透明性を確保するかだ」と語った。
税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ
<タックスワンポイント>
規制された海外不動産の節税策 最新の税制改正でついに封じ込め
「スクラップ・アンド・ビルド」の考え方に基づいて住宅を新築する日本と、一つの建物を100年を超えて使い続けることも珍しくない欧米では、同じ木造アパートであっても賃貸物件としての価値を保てる期間には大きな差がある。しかし海外不動産であっても、日本で税金を納める納税者には、国内外にかかわらず固定資産税上の法定耐用年数が一律に適用される。このギャップを利用して数千万円を節税するスキームが近年流行していたが、最新の2020年度税制改正でついに規制されるに至った。
減価償却の対象となる資産が、取得した時点で材質ごとに定められた法定耐用年数をすでに経過している場合には、「法定耐用年数の2割」を耐用年数として償却を行える。木造建築であれば本来の耐用年数は22年なので、築22年を超える中古物件を買ったとすると、その2割、つまり4年間(端数切り捨て)に分割して購入費用を償却していくわけだ。
そこで、海外の築古不動産を買う。欧米は日本に比べて土地の値段が安いので、仮に4千万円の土地と1億6千万円の中古物件を買ったとすると、この1億6千万円を4年で償却するので、毎年4千万円を「損金」として計上できることになる。不動産所得は他の給与所得などとの総合課税で、損益通算も可能だ。他の所得額にもよるが、仮に事業税含めて税率が50%とすると、なんと4年で8千万円の税金を減らせるということになる。さらに欧米の建物は数年を経過したところで大きく値落ちすることがないため、買値に近い額で売却できれば、譲渡所得税や諸経費を引いても数千万円が手元に残るというわけだ。
この節税手法については、会計検査院が16年の年次報告で「公平性を高めるよう検討」することを財務省に求めたことから、近いうちに規制されるのではないかと言われていたが、果たして20年度税制改正で、ついに規制ルールが盛り込まれた。それによれば、国外中古不動産から生じる減価償却の損失については、減価償却費が生じなかったとして扱うとされた。将来の売却時点で売却原価に含めることはできるが、各年に他の所得と損益通算ができなくなったわけだ。
この改正は、21年から実施されるが、注意したいのは「21年以降に取得した建物」ではなく、「21年以降の各年の減価償却」が対象になっている点だ。つまり改正前に購入した物件についても、この規制の効果は適用されるため、これまでの節税スキームのように規制前の「駆け込み需要」は発生しないことになる。
相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です