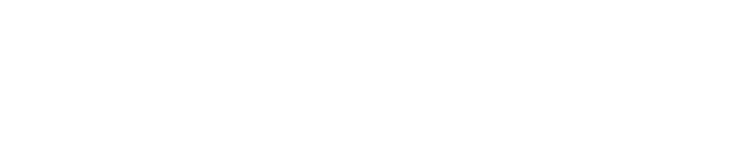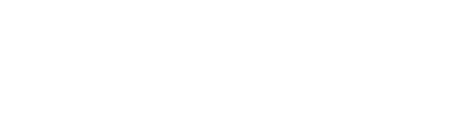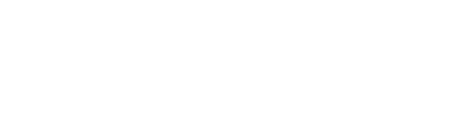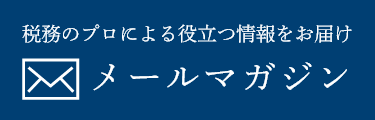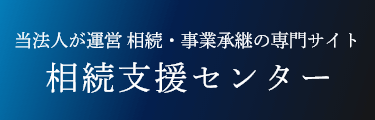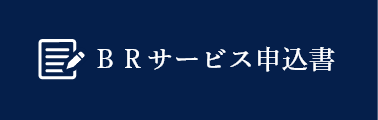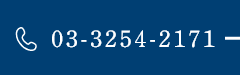Vol.0583
<タックスニュース>
バイデン政権が6カ国に報復関税を検討 巨大IT企業への課税巡り
GAFAなど巨大IT企業を対象にしたデジタル課税を巡り、米国のバイデン政権と独自課税を導入した英国などとの対立が続いている。経済協力開発機構(OECD)を通じ多国間協議が続く国際ルールについては「2021年半ばまでの合意」が目指されており、水面下の駆け引きが続いているとみられる。
米国通商代表部(USTR)のタイ代表は3月26日、英国、オーストリア、インド、イタリア、スペイン、トルコの6カ国によるデジタル課税に対する報復関税についてパブリックコメントを募集すると発表した。最大25%の追加関税が賦課される可能性があるという。米国はすでにフランスにも同様の報復関税案をまとめている。
対立の背景には、国際ルールづくりが難航していることがある。課税対象となるGAFAなど巨大IT企業の多くが米国企業のため、トランプ前政権は国際ルールに参加するかは企業の選択制にする「セーフハーバー」を主張。反発した欧州諸国を中心に、独自課税への動きが相次いだ。
新型コロナウイルス感染拡大で失業者が増える中、高収益を上げ続ける巨大IT企業への課税を世論も後押し。大規模財政支出に迫られた各国政府が新たな財源として目を付けた。
日本でもデジタル課税導入を主張する意見がある。コロナ対応で20年度一般会計歳出が175.7兆円に達し、ただでさえ主要国最悪の財政事情はさらに悪化。大規模支出の穴埋めに「コロナ復興増税」の可能性がささやかれる。
ただ、国際ルールづくりの旗振り役を務めてきた日本が独自課税に走れば自己矛盾に陥るというのが財務省の立場だ。まずは早期の国際合意へ各国の橋渡し役を果たせるかが問われそうだ。
税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ
<タックスワンポイント>
認知症保険で「万が一」に備える 貯蓄性はなく掛金は全額損金
中小企業経営者が認知症にかかってしまった時、会社は重大なリスクに直面する。例えば契約書に社長がハンコを押していても、その時点で社長が認知症を発症して意思能力がないと判断されると、契約は認められず無効になってしまう可能性がある。また中小企業への融資は銀行と社長の信頼関係で成り立っているため、社長が認知症になれば運転資金の融資が受けられなくなり、翌月にも資金繰りに困るかもしれない。さらに認知症になると議決権を行使できなくなるため、社長が自社株の大半を持っていると議決に必要な定数を満たせず、議決が必要な経営判断すべてに支障をきたしてしまう。
認知症を発症した後でも裁判所を通して法定後見人を付けるなどの事後策は取れるが、後見制度の利用には労力がかかり、その後の財産管理も硬直的にならざるを得ない。安定した事業継続や資産承継のためには、発症前に信託を設定しておいたり、自社株に認知症発症を想定した制限を付けたりするなどの対策が重要だ。
そして認知症対策として近年注目されているのが、数ある疾病のなかでも認知症にスポットを当てた「認知症保険」だ。内容の詳細は保険会社ごとに異なるが、おおむね認知症と判断されれば一時金、あるいは年金形式で、治療費やその後の介護費用を受け取れるといった仕組みとなっている。同保険については法人契約が可能なものもあり、会社が経営者個人に保険をかけ、受取人を会社にする形での契約も増えているという。これで万が一の時の資金繰りに困ることはないというわけだ。
ただし、企業が加入する生命保険といえば、高い貯蓄性や解約返戻金による内部留保の蓄積といった財務面での貢献が期待されるものが多い。その点、現在販売されている認知症保険はほとんどが返戻率ほぼゼロの掛け捨てタイプであり、貯蓄性はない。終身保険の特約で認知症保障が付いている場合などの例外はあるものの、原則として貯蓄型の保険商品のような役割は期待できないことは覚えておきたい。
だが同保険に税金面でのメリットがまったくないわけでもない。他の掛け捨てタイプの商品と同様に、認知症保険は保険料を会社の損金として落とせる。保険本来の目的である、経営者の認知症リスクへの備えとして機能しながら、会社の利益を圧縮することが可能だ。
相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です